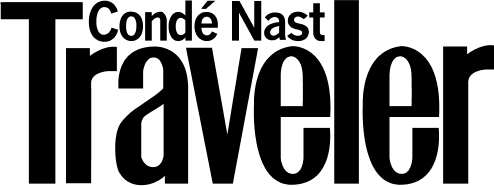到達するとプノンペン、私たちの最初の行為は夕食を探すことでした。 14年間の亡命生活を経て、本当に故郷のような味を感じた初めての食事は決して忘れられません。それは、私たちを特徴づける(そして香り豊かな)国民的調味料であるプラホクであることがぴったりでした。母が作った素晴らしい調理済みプラホクによく似たバージョンを準備している人を見つけました。クルンスパイスペースト、豚ひき肉、タマリンドの若い葉を混ぜ、バナナの葉で包んでグリルしたものです。私は子供の頃、生のプラホクの味を一度も味わったことはありませんでしたが、その日の甘美で刺激的な魚は私にとって、カンボジアの味。私は目を閉じて、懐かしい香りを飲みました。安堵感と幸福感が私に押し寄せました。結局のところ、失われた世界に不可欠な何かが生き残っていたのです。
その感覚は、プラホクを最初に数口食べたときまで続きました。戦後のサイゴンにいるとどんなにお腹が空いていると思っていても、1984年にカンボジアで目撃した光景に対する備えは何もありませんでした。人々は想像を絶する飢えと惨めさの中で、ほとんど救われずに暮らしていました。だからこそ、クメール・ルージュが政権を失ったにもかかわらず、私たちカンボジア人は依然として数十万人規模でタイに向かって流れ込んでいるのです。そしてタイは猛攻撃に動揺した。
プノンペンは暗くて不自由な街だった。ここは、幼い頃、弟の能のモトの前できらびやかな通りを駆け回っていた私を魅了した優雅な首都ではありませんでした。威厳のある古い建物は欠けて色あせ、あるいは通りに崩れ落ち、中庭や歩道は草が生い茂って座屈していた。車、シクロ、路面電車の売り子、そしてバイクに積み重なった家族連れの大都市のいつもの喧騒は、警戒心のようなざわめきを静めていた。エレガントなドレスを着て漂う若い女の子も、衣服を着て教会や塔に引きずり込まれる、ゴシゴシと甘やかされて甘やかされた子供たちも、窓から漂ってくる音楽のささやきもありませんでした。
サフラン色のローブを着た修道士数名が何とか生き残っていた。朝になると、彼らは以前と同じように静かに列を作って闊歩した。しかし、輝かしい古い教会、仏塔、修道院のほとんどは、今では遺棄された砲弾か、徹底的に破壊されており、クメール・ルージュは多くの礼拝所を破壊していた。他には倉庫、集会所、刑務所、絶滅現場として再利用されていました。彼らは国立図書館と公文書館をキッチンに、壁に囲まれた庭園を豚小屋に改造したのです。本や記録は焼かれてしまった。私たちの書かれた歴史薪として使われます。
都市は意味のある意味で機能しませんでした。電気は稀で、きれいな水はほとんど入手できませんでした。ゴミや下水がいたるところにありました。商店や企業はシャッターが閉まり真っ暗で、多くの家が空き家となった。ごくたまに見かけるモト(あるいは長い荷車を牽引するモト・リモーク)を除けば、道路を走る車両は軍用トラックだけだった。誰もが同じ考えを持っているようでした。空き家に引っ越して、路上で売るためにいくつかの悲惨な商品を見つけました。戦後のプノンペンは不法占拠者、ハスラー、物乞いが住む荒れ果てた都市だった。こけた頬と突き出た肋骨。ベトナム兵もお腹が空いて取り憑かれているようだった。
しかし、ネズミとハエは繁栄しました。
チャンと私は、ベトナム語を話す人がたくさん住んでいる粗末なアパートのベッドを借りました。あたかもこの都市の住人の大多数が最近ベトナムから移住してきた人たちであるかのようだった。新旧のプノンペン住民の間には、相互不信の暗い空気が漂っていた。多くのクメール人はベトナム人を救世主というよりも占領者として見ていた。ある意味、彼らは両方だった。
私たちはどのカテゴリーにもきちんと当てはまりませんでした。その時点では、占領と帝国の政治は私たちにとってほとんど重要ではありませんでした。私たちの考えは、ベトナムとカンボジアの両国をできるだけ早く追い出すことでした。私たちは北西に向かってバッタンバンに向かい、そこからポイペトのタイ国境検問所に向かう予定でした。
私たちは人々に交通手段を見つける方法を尋ね始めました。バッタンバンやその先への旅行は非常に危険だという同じ答えを何度も聞きました。ベトナム軍はクメール・ルージュの残党を西のタイ近くの森林に押し込み、そこでは依然として激しい戦闘が続いていた。
チャンも私も何を信じてよいのか分かりませんでした。私たちはサイゴンで聞いた噂に盲目的に行動していました。しかし、タイ国境から遠ざかるほど、その噂の正確性は低くなることはすぐにわかりました。私たちがベトナムで聞いたことは事実上すべて間違っていました。今、私たちがすべきことは、下流に流れる小枝のように、後戻りすることなく、進み続けることだけでした。
私たちは兵士でいっぱいの車に乗っていれば安全だと願いながら、ぎっしり詰まった軍用トラックに乗り込み、考えられる限り最悪の道路をガタガタと音を立ててバッタンバンに向かって進みました。私はフレンドリーなベトナム兵の隣に座っていましたが、彼は私たちにどこへ向かうのかと尋ねました。何らかの理由で、私たちは彼を信頼し、私たちの計画を彼に伝えました。 「それは危険な冒険のようですね」と彼は言った。 「しかし、少なくともあなたにはお互いがいます。助けがあれば何でもできるよ。」私たちは微笑みながら、それが本当であることに同意しました。
現在のプノンペンの市場での魚売り
アナドル/ゲッティイメージズバッタンバンでは、私はチャンと一緒に歩き、思い出を呼び起こす可能性のあるものを探しました。私たちの家がどこにあったのか分かりませんでした。見覚えのある古い植民地時代の建物がいくつかありましたが、私の教会と学校はなくなっていました。さらに言うと、機能している教会、学校、塔などをまったく見た記憶がありません。多くの建物が崩れて空き家になっていました。ドアのある家はほとんどありませんでした。とにかく、誰も盗む価値のあるものを持っていなかったので、なぜ閉じ込める必要があるのでしょうか?ほとんどの店やレストランも閉まっていました。しかし、少なくとも私の記憶通りの市場は、早朝には魚や野菜を売る業者で賑わっていましたが、昼になると静まり返りました。
バッタンバンでの最初の朝食は、感覚のフラッシュバックの洪水を引き起こしました。ヌム・バインチョク(「クメール麺」)は、私が小さかったころ、市場で買ったお気に入りの屋台の食べ物の 1 つでした。私は手で押し出し、軽く発酵させたビーフンと、それを使って作った心安らぐ料理の数々が大好きでした。
中国にビーフンを持ち込んだ、トゥン・チェイという名の賢いクメール人の英雄についての民話があります。伝説によると、人々は彼が作ったヌム・バインチョクをとても気に入ったので、皇帝のために麺を作るよう招待されたそうです。
米を細長い麺に変えるのに必要な工程の多さは、意欲的な「クメールヌードル」起業家たちのほとんどを思いとどまらせるのに十分だ。簡単な概要は次のとおりです。
- お米を熱湯に浸して柔らかくします。 (浸したお米を炊き上がったお米と混ぜて次のステップに進むこともできます。)
- それを石臼で挽いて生地を作ります。
- 生地を袋に入れて余分な水分を絞ります。
- 生地を発酵させて、乾燥した粘りのある小麦粉を作ります。
- 小麦粉を茹でて生地を固めます。
- 生地を乳鉢と乳棒で潰し、弾力のあるペーストを作ります。
- 生地ペーストを原始的な押出機、つまり穴の開いた金属の底を備えたシリンダーに入れます。
- 長い木製レバーの端に座り、生地を押出機に通して沸騰したお湯のポットに押し込みます。
- 麺が浮き上がってきたらすくい上げます。
- 麺を洗い、冷水に入れます。
- 指一杯分の麺を水から引き上げ、余分な液体を絞り、蓮やバナナの葉を並べた幅広の平らなバスケットの上で芸術的な渦巻き状に折ります。
- 明るいうちに麺を市場に運びます。
- 全部売って手順1に戻ります。
ヌム・バインチョクが食べたくなったら、カンボジアのどの町でも、早朝にカゴを肩に担いでいる睡眠不足の女性たちに注目してください。毎日手作りするには、気概と忍耐が必要であり、露天商の並外れた労働倫理が必要です。どの地域にも、独自のスープ、ソース、トッピングを備えた独自の「クメール ヌードル」料理があります。その最初の朝、バッタンバンでは、私たちはヌム・バインチョク・トゥク・サンロール・クメール料理を食べました。レモングラスとクルン・スパイス・ペーストで作ったスープのような魚のグレービーソースに春雨を入れ、ハーブ、バナナの花、生野菜を添え、甘くておいしいソースであるトゥク・オムリスをトッピングしました。バッタンバン原産で、ココナッツミルク、唐辛子、パームシュガー、ニンニクで作られています。
私たちは、ベンダーがスタンドのそばに設置したベンチにしゃがんで満足したダイナーの集団に加わりました。私は、ナム・バインチョクは座っていても立っていても適切に摂取できないと確信しています。適切な体験をするには、しゃがんで食べる必要があります。それ以外の方法では美味しくありません。
急いですすった朝食は、私の人生で最高の食事の 1 つでした。それは故郷と幸福のようなもので、私が完璧なものとして覚えておくことにした過去のようなものでした。幼い頃、私はぬるぬるしたスープが大好きでした麺毎朝作りたて。おそらくそれは、私が普段それらを食べることを許されていなかったからかもしれません。代わりにいつもkuy teavを持っていました。しかし、その朝、15年ぶりにバッタンバンに戻ってきた人は誰も私を引き離すことはできませんでした。
より抜粋スロー ヌードル: カンボジアの愛、喪失、家族のレシピの回想録チャンサ・グオン著、キム・グリーン著。 著作権 © 2024 by Chantha Nguon.チャペルヒルのアロンキン・ブックスの許可を得て抜粋。無断転載を禁じます。