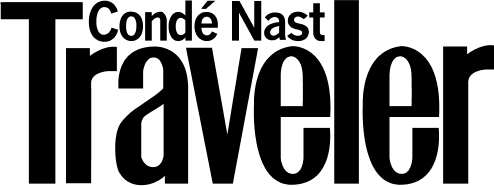ペットは家族ですよね?それはペットの飼い主なら誰でも持っている暗黙の了解です。つまり、パグルのハンクがクリスマスカードを作り、マンクス猫のスナップルが誕生日パーティーを開くことになります。それは両方が来るという意味でもあります家族旅行(あなたはあなたのものを置かないでしょう子供結局のところ、犬小屋の中です)。ペットを飼っていない人にとって、そのほとんどは問題ありません。それぞれ自分のものに。ただし、休暇中に突然、ルームサービスのトロリーが通過するたびに吠える研究室とホテルのフロアを共有することになった場合や、ハッピーアワーが「ヤッピーアワー」になった屋外テラスにいる場合は別です。 。」この場合、誰が譲歩するのでしょうか?すべてのホテルはペット同伴可であるべきでしょうか、それとも子犬の入場を禁止すべきでしょうか?それはあなたがその新しい場所にどれだけ留まりたいかによる北部最近インスタグラムで話題になっているしかし、フィドのためのスペースも作ります。私たちはそれをやり遂げます。
ペットには居場所がある
「ますます多くのホテルが、ペットに優しい列車, 4本足の友達と一緒に旅行したい人はそれができるのは素晴らしいことだと思います。いつか私もその一人になるかもしれない。もちろん、これがここでの大きな注意点ですが、「ペットに優しい」というのは「ペットに夢中」という意味ではありません。犬のマッサージや子猫のカクテルアワーを提供するホテルは、私が行きたい場所ではありません。彼らは20歩行きすぎています。インスタグラムのフィードがペットのアカウントでいっぱいになっている人の意見です。インターネットの隅っこをインターネット上に残しておこう。」ミーガン・スパレル
「私は家族の誰よりも自分の猫を愛している可能性があります。そこで、私はそれを言いました。だから、私にとって、それは明らかですもちろんホテルがペットを許可すべきかどうかを議論する瞬間。幼児を家に残しておかなければいけないと言われたくないですよね?ただ、相手の気持ちが全く動かないわけではない。確かに、ペットの毛は抜けて汚くなりますし、アレルギーに関するもう一つの正当な議論もあります。だからこそ、ホテルは常にペットのいない部屋を確保し、動物嫌いの変人たちにオプションの環境を提供すべきだと私は思う。つまり、私と同じように正論を持った他の人たちです。」ララ・クレイマー
自分で犬舎を探す
「昨年の夏、オープンしたばかりのホテルについて聞いたのを覚えています。見た目は豪華で完璧でした。長い週末の休暇自然の真ん中で。レストランも素晴らしいものになるはずだった。その後、犬を許可していると聞きました。それが私にとってその場所の終わりでした。アレルギーを持ち、犬に対して生涯恐怖を抱いている私は、犬の飼い主の家でのディナーパーティーに招待されるだけでもひるみます。飛び跳ねたり、舐めたり、匂いを嗅いだり。犬の舌は私の肌にサンドペーパーを当てたように感じます。彼の唾液は、百万本の小さな燃える針のようだった。そのため、私はペット可のホテルを避けるようにしています。ホテルのベッドの上で犬がはしゃぎ回る姿を想像すると身がすくんでしまいます。ホテルの掛け布団やカーペットに肉球や毛皮(それとも毛?)が落ちていませんか?ああ。あなたが自分の犬をかわいいと思っているのはわかりますが、おそらくそうでしょう。しかし、私たちが同じ屋根の下でホテルに滞在しているときは、誰もが犬を愛しているわけではないので、ペットなしがデフォルトであるのは当然だと思います。それに、数晩は愛犬と別れることができないので、ジルテックを飲んだり、ロビーで水入れを脇に置いたりして休暇を過ごしたくはありません。」ローレン・デカルロ
「ペットを家に残しておいてください。理由はたくさんあります。第一に、アレルギーです。ほとんどのホテルでは、ペットが滞在するたびに HEPA グレードのエアフィルターと掃除機を使用していないと確信しています。第二に、吠えます。特に迷惑なのは午前 2 時頃です。そして、犬は家では行儀が良いかもしれませんが、新しい、そしておそらく狭い場所でどのように行動するかは当然ではありません(ここで「小さな子供はどうするか」という話が戻ってくるのは知っていますが、それとは反対です。何個第三に、臭いと汚さ ペットを飼っている人は誰も自分の家が臭いとは思いませんが、ペットを飼っていない人は家に入るとすぐに臭いを嗅ぎます。ホテルでもその臭いがするのは嫌です。散らかっている部屋でも同じです。ペットやペットが事故に遭った部屋には泊まりたくありません(もう一度、実際に掃除がどの程度行われるかを考えてみましょう)。ペットの旅立ち — カーペットはそうではないと思います蒸したり、ベッドスプレッドを洗濯したり)、間違いなく服に付くであろうペットの抜け毛には対処したくないのです。」 —レベッカ・マイズナー



%20Getty%20Images_CNT%20UK_Sophie%20Knight.jpeg)