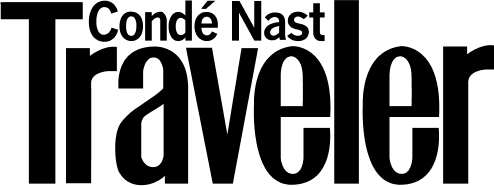最近のある午後、ニューデリーのインペリアルホテルのロビーは、イタリア製のスーツを着たインド人ビジネスマンと、カーキ色のサファリ服を着た裕福な観光客で賑わっていた。白い大理石のアトリウムに座って、私は他の訪問者が 5 つ星ホテルに期待するものと考えるかもしれない光景に興味をそそられました。シャネルのブティック、そびえ立つ花のディスプレイ、19 世紀に考案されたアールデコ様式の古典を囲む輝く柱などです。 1930 年代に当初の都市計画が策定され、当時ニューデリーは大英帝国の中心になろうとしていました。
ここにも歴史がありました。 1970年代の数年間、私は衣料品会社を経営しながらデリーでパートタイムで暮らしていました。当時、インペリアルはロサンゼルスのシャトー マーモントの老朽化した亜大陸版でした。カビの臭いがし、湿気の多いエアコンのせいでカーペットは汚れて波打っていました。それでも、コンノートプレイス周辺の小道にひしめき合うヒッピーホテルやバックパッカーホテルよりもはるかに優れていました。インペリアルは、骨董品や宝石のディーラー、ハシシの密輸業者、闇市場の通貨詐欺師、悪党、軽犯罪者、そして私のような在留外国人にとっての社交場でもありました。
私たちはそれを「ホテル帝国主義」と名付けました。窓のないオーク材のパネル張りのバーは正午までにいつも満席で、客層はリックズ カフェとスターウォーズのあのバーの混合でした。彼らは何時間も椅子に座り、刺激の強いインディアンタバコを吸い、ロージーペリカンビールを飲みながら陰謀を企てました。外には、王室のヤシの木に囲まれた美しいプールがありました。 1マイル離れたところでもその匂いを感じることができた――念のため言っておきますが、塩素ではなく、ハシシの匂いです。甘い香りが漂い、巧みに巻かれた関節が、擦り切れそうな寝椅子から次の寝椅子へと渡っていきました。当時はプールが不足していたため、気温 110 度の日にはインペリアルは真のオアシスでした。私は泳いで、ボロボロの白い制服を着たウェイターが持ってきた新鮮なライムソーダを飲みました。インペリアルでは何でもありだった。警察は一向に来ないようだった。
さて、ラージ風のロビーで高価なエスプレッソを飲みながら、この宿泊客の中にここで何が起こっていたのかを知っている人はいるのだろうかと疑問に思った。どうでもいい、昔のインドの多くと同じように、あの古い群衆はもういなくなってしまった、と私は思った。そして、現在は多くの点で状況がはるかに良くなっている。かつては進歩に対して不変の抵抗力があるように見えたインドは、1990年代の経済改革によって終末の予言を回避し、何百万人もの人々を貧困から救い出し、長年妨げられてきた起業家階級を解放した。その結果として生じた西部開拓時代の経済の影響で、それ以来何度も私が帰国するようになりました。最初はテレビで働いていたときで、最近では新しいモバイル革命に乗っているデジタル新興企業をチェックするためでした。しかし、40年以上にわたって私を本当に惹きつけてきたのは、まったく別のことでした。
私のインドへの旅は、1972 年のある苦い 1 月の日から始まりました。そのとき、私は他の冷静な 20 代と同じように、ニューヨークの広告代理店での閉所恐怖症の仕事を辞め、ヨーロッパに向けて出発しました。その夏、ギリシャで私は海辺のカフェで美しい女の子とおしゃべりしました。インドから戻ってきたばかりの彼女は、神秘的な東洋の物語、つまり「地上最大のショー」で私を楽しませてくれました。私はその場で予定を変更し、イスタンブールへ向かいました。そこから、車、バン、バス、トラックに乗って、イラン、アフガニスタン、パキスタンなど、もう行くことのできない国々を巡りました。当時、人々はいつもピースサインを見せていました。
フレストンと友人、ラジャスタン州アブ山にて、1976年。
写真提供者: ケン・クックパキスタンから陸路でインドに入ると、すぐにもっと努力しなければならないと思いました。アムリトサルの混雑の中で、私は急性の見当識障害を感じました。やがてこの感覚を味わうようになりました。私は毎日迷子になるつもりでした。そして夜にホテルに戻り、ドアを閉めて息を吐きました。インドはまだ比較的新しい国でした。その信条は「自立」でしたが、人々は世界から切り離された息苦しい社会主義制度の下で非常に苦労していました。この国では国内の報道機関や映画産業が盛んでしたが、電話もテレビもほとんどなく、自動車もほぼ 1 種類しかありませんでした。洋装の人も珍しい。貧困は圧倒的で、屈辱的なものでした。歩道や電車のホームには、ゴミに囲まれて眠っている人々の列が詰め込まれていました。物乞いのコロニーは橋の下に住んでいた。
しかし、すべてを乗り越えることには高揚感がありました。オールドデリーの迷路を疾走するスクータータクシーのネズミのような猛スピードから生き延びるだけでも、小さな勝利でした。私はここに留まり、その場所についてできる限りのことを学ぶことを誓いました。これだけ多くのことが英語で書かれていたのは良いスタートでした。私は、避妊具や釣り針を宣伝するアムリトサルのウィンドウや、おもちゃやトイレを宣伝するデリーの店など、ありそうもないことを約束する店の看板が大好きでした。かつてイーグルスが歌ったように、インドは「いつもすべて」のように見えた。矛盾と混沌を抱え、独自の高速車線で生きている複雑な国だ。
今日、インドのほとんどの都市には高速近代化の兆候があふれていますが、この国の商業首都であるムンバイほど顕著なところはありません。ムンバイは人口 2,100 万人 (ニューヨークとロサンゼルスを合わせた人口のほぼ 2 倍) の都市であり、その街路は現在、完全に整備されています。 BMW がひしめき、ブルー フロッグやグッド ワイフなどの名前の高級レストランが立ち並んでいます。ここでは、金持ちと貧乏人、敬虔さと俗世が、西洋人には理解しがたい形で共存している。ムンバイ最大のスラム街の一つにそびえ立つのは、インドで最も裕福なムケシュ・アンバニの 27 階建て、40 万平方フィートの邸宅で、168 台の車のガレージと 3 つのヘリポートを備えています。しかし、アンバーニがそこに滞在することはめったにないため、ほとんどの夜、建物は空いていて暗いままです。ある時点で、その建設はヒンズー教の建築原則に違反し、不運をもたらす可能性があると決定されました。
「ラジャスタン州では、男性も女性も宝石を身につけています。ここでは、商人の手が宝石で覆われています。彼の金のペンダントには、無敵の女神ドゥルガーが描かれています。」とヴェルニエールは書いています。
最近の旅行では、ムンバイの空港近くのデジタル新興企業にチェックインした後(iMac がたくさんあるオフィスで、若いスタッフが公衆排尿の惨劇と戦うことを目的とした公共サービスのビデオを見せてくれた)、ジャイプール文学館に寄り道した。お祭り。インドはウパニシャッドからアミタブ・ゴーシュに至るまで文字に深い敬意を払っており、ラジャスタン州の歴史あるピンク色の都市で開催されるこの祭りには約25万人の参加者が集まる。時々、TEDカンファレンスに来たような気分になった。スマートフォンを持ち歩くクリエイターたちが、GoogleとFordが後援する野外テントの席を争っていた。市内の最新のホットスポット、バー・パラディオでは、砂漠の空の下、クジャクが焚き火台の周りを歩き回っていた。これは、大規模な干ばつと食糧不足の最中に私が訪れた1973年に訪れた、ほこりっぽく汚いジャイプールとはまったく対照的でした。当時は、懇願する母親たちがうつろな目をした赤ん坊を私の腕に押し込んでいたのです。
それでも、古いスピードバンプは現代への道でも耐え続けます。交通渋滞と激しい暴風雨に巻き込まれたスクータータクシーの後部座席から、私はこのことを考えました。バス、自転車、オートバイ、牛車が草の生い茂ったロータリーの周りで空きを求めて競い合い、髪を切ったり、歯を抜いたり、ピンクの風船を売ったりする人々であふれていた。進歩し、大混乱に遭遇します。その夜遅くに私はパラディオに戻りましたが、そこはフェスティバルの参加者で溢れていました。このバーのマネージャー――ウィスコンシン州出身で、インドの避けられない非効率さに明らかに絶望している――は、「外国産のワイン」がなくなりそうだと私たちに告げ、こう付け加えた。時間。"
そして、現代のインドがほとんど寄せ付けられていない場所がまだあります。マーク・トウェインが「歴史よりも古い」と呼んだインドの聖地で最も神聖なバラナシを例に挙げてみましょう。 。 。すべての細胞が寺院、神社、またはモスクになっている宗教的な集団です。」ここは死が全面的に表れている場所でもあり、多くの西洋人にとって不快な思いをさせている。自分の運命に直面すると、私たちは否定する傾向があります。しかし、バラナシはヒンドゥー教徒に対して、ある種の「刑務所から自由に出られる」カードを提供している。死亡するかここで火葬された場合、モクシャを達成して再生を逃れることができる。そして、死神を待ち構える多くの高齢者、死体を縛り付けた車、マリーゴールドで飾られた竹担架に遺体を載せた葬列の姿が見られる。彼らは迷路のような路地を通って、ガンジス川のほとりに築かれた「燃えるガート山脈」に向かい、そこで火葬の順番を待ちます。
「ある男」のバンに乗ってヒマラヤを走るフレストン、1972年。
提供:トム・フレストン夕暮れ時、私は自転車人力車を川に向かってできる限り遠くまで連れて、混乱の中に出かけました。通りは人とバイクで混雑しており、神聖な牛は誰にも邪魔されずに歩き回っていました。 (私はサリーショップの中を歩き回っているのを見つけました。)最終的に私はガートの泥だらけで不規則な階段を駆け下り、巡礼者や聖なる人の群衆をかき分けて川の端まで行き、そこでガイドが小さなボートを確保しました。
バラナシでは、外国人は単なる観察者であり、ボートは完璧な観察所です。ガンジス川にはマハラジャが建てた崩れかけた宮殿が立ち並んでいます。巡礼者はこの水を沐浴し、歯を磨き、さらには水を飲んで身を清め、穢れを受け付けません。私は1年前に、2羽のカラスが背中にうつ伏せになって漂流する死体を目撃して以来、浮遊死体を探していました。川の上は寒くてじめじめしてきました。小さな受け皿にキャンドルが浮かんでいました。葬式用の薪の火が霧の中でオレンジ色に輝いていました。私は、インドの奥深くにある、少し神聖な気分を感じながら、あらゆる感覚が生き生きとして、釘付けになって座っていました。この国は、1972 年当時には考えられなかったような、消費主義と現代化に向けて急ピッチで進んでいるかもしれませんが、バラナシではそのようなことはどこにも見られません。 (どこにも、つまり、側面にインド州立銀行の絵が描かれた近くのボート以外にはありません。マーケティングには常に長い手があります。)私は、この川のすぐ近くに何度もいたことを思い出しました。アレン・ギンズバーグが表現したように、シーンの「変貌した安らぎ」に夢中になった若者が、40年経った今。それはいつものように、これまでと同じでした。