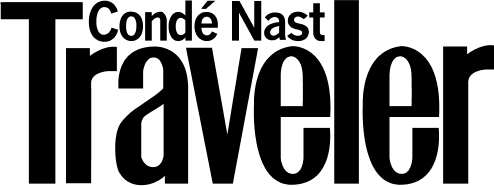このエッセイは、監禁後の旅行についてのシリーズの最初のものです。この夏、次の作品を探してください。
刑務所を出た翌日、私は8年ぶりに海の空気を吸いました。
オーシャンドライブを裸足で散歩することにしたマイアミ、手作りの木製ビーズのブレスレットや吹きガラスのボウルを販売するベンダーを通り過ぎます。バイカーやローラースケート選手海辺の遊歩道を巡っていました。近くのバーからはレゲエ音楽が漂っていた。片手に特大のモヒート、もう片手にシュラスコの串を抱えた私は、傘や日光浴客が点在する白い砂浜を越えて大西洋を眺めた。それは私が子供の頃、家族旅行中に泳いで育った同じ水だった。ジャージーショア。海の端は子供の頃から私にとって聖域であり、黒く染まったジングル貝、黄褐色のツブ貝、カブトガニの殻の破片が散らばるザラザラとした冷たい水面に足を広げたくなるのがいつも私を惹きつけます。空気と食べ物が必要なように、砂と海が必要です。
しかし、本質的に完全に自由であることが、今の私には現実とは思えませんでした。
2014年に財産犯罪で逮捕されたとき、私は北フロリダに住んでいました。その前に住んでいたのはフィラデルフィア、私の故郷。しかし、私の刑務所であるエバーグレーズ矯正施設はマイアミから西に30マイル離れたところにあり、私は一度も訪れたことのない街でした。海岸沿いの大都市のヨットやナイトクラブは何百万マイルも離れたところに感じられましたが、フレッシュマンゴージュースやカルチェラタンについて聞いた話を聞くと、どういうわけかいつも居心地よく感じられました。
このようにして、マイアミの痕跡が私の刑務所に到達しました。私は日曜日にマイアミ・ドルフィンズの試合をよく見ていました。刑務所の寝台の隣の窓から、休日には花火大会が見えました。そして、マイアミの地元の人々は、お気に入りのレストラン、音楽シーン、街の有名人について教えてくれました。フアンは、6 番街にある叔父のキューバ コーヒー ショップについて話しました。ガルシアさんは、嵐が通過した後の湾の匂いが大好きで、「まるで生臭い天国のようだ」と彼は言いました。
8 年間の懲役刑の間、私はこの活気に満ちた多文化都市を訪れることを夢見ていました。そして2022年の大晦日、私が解放された翌日、ついに解放されました。
***
エバーグレーズでの最後の日は、約 3,000 日間の収監中、いつもと同じように始まりました。午前4時に拡声器とサイレンでびっくりして目が覚め、食事の準備をするように言われました。せっかちな囚人たちが食事やギャングの噂話のために列をなした。喧嘩が勃発した。常に状況認識が高まった状態で生活することにストレスを感じていました。ベージュのコンクリートの壁と鉄筋が、長い間私の人生を彩っていました。私は、バイオリンの音、新鮮な洗濯物の匂い、ドクターペッパーの味など、ほとんど覚えていないものに戻りたいと切望していました。しかし、解放されるまであと 6 時間という時点で、どのようにして外の世界に再び順応していけばよいのか、不安を感じていました。

作家のダニエル・ポワンデュジュールが、何十年も待ち望んでいた帰国について語る。
私は刑務所のテレビ室の金属製のベンチに座ってTMZを観ながら、私をここに連れてきた決断について考えました。鎮痛剤の乱用が最悪だったとき、私は依存症を支えるために財産犯罪を犯しました。自由、尊厳、尊敬、愛、それがどれだけの代償を払うことになるのか、私はまったく知りませんでした。家族に会うのは 10 年ぶりでしたが、もうすぐ会えることに興奮し、緊張していました。そして、その日家に帰るのは私だけだということもわかっていました。鉄格子の窓からはエバーグレーズの湿地が垣間見え、九官鳥やカミツキガメが刑務所の門のすぐ外で餌を食べていました。私は自分の名前と矯正局の番号が呼ばれて釈放を告げられるのを待ちました。
武装した警官に守られながら、私が蛇腹状のカミソリの柵から外に出ると、私の指導者であるアレックスが反対側に立って私を待っていました。 4年間、私は彼が刑務所内に作った男性グループを率いており、私たちは友人になりました。背が高くて社交的で、元レストラン経営者で刑務所内の男性を助けることに尽力していた彼は、私にとっては父親や継父が父親のような存在ではなかったときの父親のような存在でした。彼は白髪の老政治家のような風貌で私に挨拶し、カーキ色のパンツとポロシャツを私の手に投げ渡し、レクサスに着替えるように言った。人々が刑務所を出るとき、それは「家に帰ってくる」と表現されることがよくあります。しかし、アレックスは比喩的に私を家に迎えてくれただけではなく、マイアミ中心部のすぐ外にある町、ケンダルにある彼の家で一週間私をもてなしてくれました。
「あのフェンスを振り返って、もう後戻りできないと知るのはどんな気分ですか?」彼は私に尋ねました。
あまりにも圧倒されて返事ができなかった。
***
刑務所を出たにもかかわらず、私の一挙手一投足が誰かに監視されているように感じました。中には常に警備員がいて、あなたの目の前にいて、私が一時的に国の所有物であり、彼らがその所有物の管理を非常に真剣に受け止めていたことを毎日思い出させてくれました。ビーチでは、私が規則を破ったのを捕まえようと待っている刑務官はいない、と自分に言い聞かせなければなりませんでした。サウスビーチの周りを巡回しているバイク警官は、歩いている私を一瞥も見ませんでした。私は詐欺師ではありませんでした。私を刑務所に送り返すのを待っている人は誰もいませんでした。私は自分の時間を務めました。私はここに属していました。
夕暮れが近づいてきたので、大晦日、笑い声とお祭り騒ぎがバーから響き渡りました。ランボルギーニとポーチがバンパーからバンパーへと詰め込まれ、エレクトロニック ダンス ミュージックを大音量で鳴らしながら、オーシャン ドライブを這っていきました。ネオンがストリップのアールデコ様式の建築を照らしました。私は足の砂を洗い流し、アレックスと彼の妻に会うためにダウンタウンのハードロックカフェまでウーバーを捕まえました。
何ヶ月もの間、夫婦はそのことを自慢していましたマイアミのレストラン、彼らが私をどれほど誇りに思っているか、そして自分たちの街を自慢することにどれほど興奮しているかを電話で私に言いました。夕食はビスケーン湾を望むテーブルで新鮮なサーモンとアスパラガスをいただきました。私は椅子にもたれかかり、魚が口の中でとろける様子に驚きました。緑はとてもシャキシャキしていて、パチパチと歯ごたえがありました。私はパンに添えられたプラムソースとアボカドスプレッドを味わい、8年間食べてきた謎の肉について考えました。もう二度と混雑した食事の列に並び、栄養失調になるか定期的に食べ物を食べるかの選択を迫られることはないだろう男性を食中毒にさせた。
残りの夜にはさらに大きな計画がありました。夕食後、私たちはベイフロントパークの円形闘技場まで歩き、そこでコンサートで新年を迎えました。ピットブル—できる限りマイアミと同じくらいです。ショーが近づくとサブウーファーが鳴り響きました。芝生の上でステージはほとんど見えませんでしたが、幸せな気持ちでいっぱいでした。周りに人が多すぎて、最初は私が不安になるのではないかとアレックスも心配していましたが、私は新しい家族に囲まれたような安心感と温かさを感じました。
ショーの途中で花火が空に打ち上げられ、酔った観客は悲鳴を上げ、口笛を吹きました。ビスケーン湾の近くにあるオレンジボウルの大きな時計はカウントダウンを続けていました。3分10秒…3分9秒…私は時計が切れるのを何年も待ちました。でも今は、現状に満足していました。
「今夜は特別じゃない?」ドイツ人旅行者が振り返って私に尋ねました。 「最初からやり直してもいいよ。」
依存症、結婚生活、子供たちとの関係、キャリア、信念、自由の喪失など、もう一度やり直したいと思ったときのことを思い出しました。 「その通りです」と私は言いました。 「それは特別です。」
真夜中が近づくにつれ、花火は大きくなっていきました。カラフルな爆弾がマイアミ中心部上空で爆発した。黄色と青の火花が空を横切りました。写真を撮ろうと新しいスマホを取り出したのですが、私がいない間に携帯電話の仕様が大きく変わっていて手探りでした。今年最後の10秒が消え去り、過去の過ちを残したとき、私は目に涙を浮かべながらアランを見つめた。
私たちがビスケーン湾沿いの高層ビルにあるアレックスのコンドミニアムに戻ったのは、正式には 2023 年の明け方でした。私はバルコニーで葉巻を吸い、手すり越しに木製の橋脚に打ち寄せる水面を眺めながら、ある世界を離れて別の世界に入るというカルチャーショックを和らげ、また平和なチャンスを与えられたことに感謝した。ヤシの木が揺れ、シロトキのつがいが浅瀬で草を食んでいた。欠けていく月の下でボートの明かりがさざ波を散らし、深夜の夜会では笑い声が湾に響き渡った。私はバルコニーのすぐ上のハンモックで眠りに落ち、何年かぶりに安全を感じました。
***
次の 1 週間にわたって、私は生の感情と新鮮な経験に出会いました。それは、タコスでした。リトルハバナキューバのサルサ音楽が流れている間。ウィンウッドアート地区の落書きされた建物。湾を望むビストロでコーヒーを飲みます。マイアミでの最後の日、私はアレックスの車を借りて、夜明けにビーチまでドライブし、自転車を借りて海沿いの道を走りました。空は地平線上の琥珀色の斑点を除いて、不気味な傷のある紫色でした。 30 番街からスタートし、ヴァンス ジョイの「ミッシング ピース」が携帯電話から流れる中、由緒ある通りを通りながら南へペダルを漕ぎました。フォンテーヌブロー ホテル。ビーチには誰もいなくて、何年ぶりかで私は完全に一人で考えを巡らせました。
8 番街で私は自転車をロックし、つま先を砂の中に深く押し込みながら波に向かって歩きました。遠くでクルーズ船が霧笛を鳴らしていた。私は浜辺に座って、桃色の雲から昇る真っ赤な太陽が言葉では言い表せない美しさで生まれるのを眺めました。私は失ったすべての年月、生きて生還できたこと、すぐに家族と再会できたことを思い、静かに泣きました。外出して最初の 1 週間を、この魔法の町のレンズを通して人生が提供する喜びや素晴らしさを体験して過ごしたので、私は楽観的で将来に希望を抱いていました。友情を育んだり、新しい食べ物に挑戦したり、妹と電話で話したりすることなどです。空気中に塩の匂いが漂います。それはすべて、私が間違った決断を下した場合に何を失うことになるのかを思い出させました。
私は深呼吸をした。日の出の光に負けないほど暗い夜はありませんでした、そして私はそのことに感謝しました。
この記事は、刑務所ジャーナリズムプロジェクト、投獄された作家をジャーナリズムの訓練し、その作品を出版する非営利ジャーナリズム組織。 PJP ライターによる他の作品も読むことができますここ。